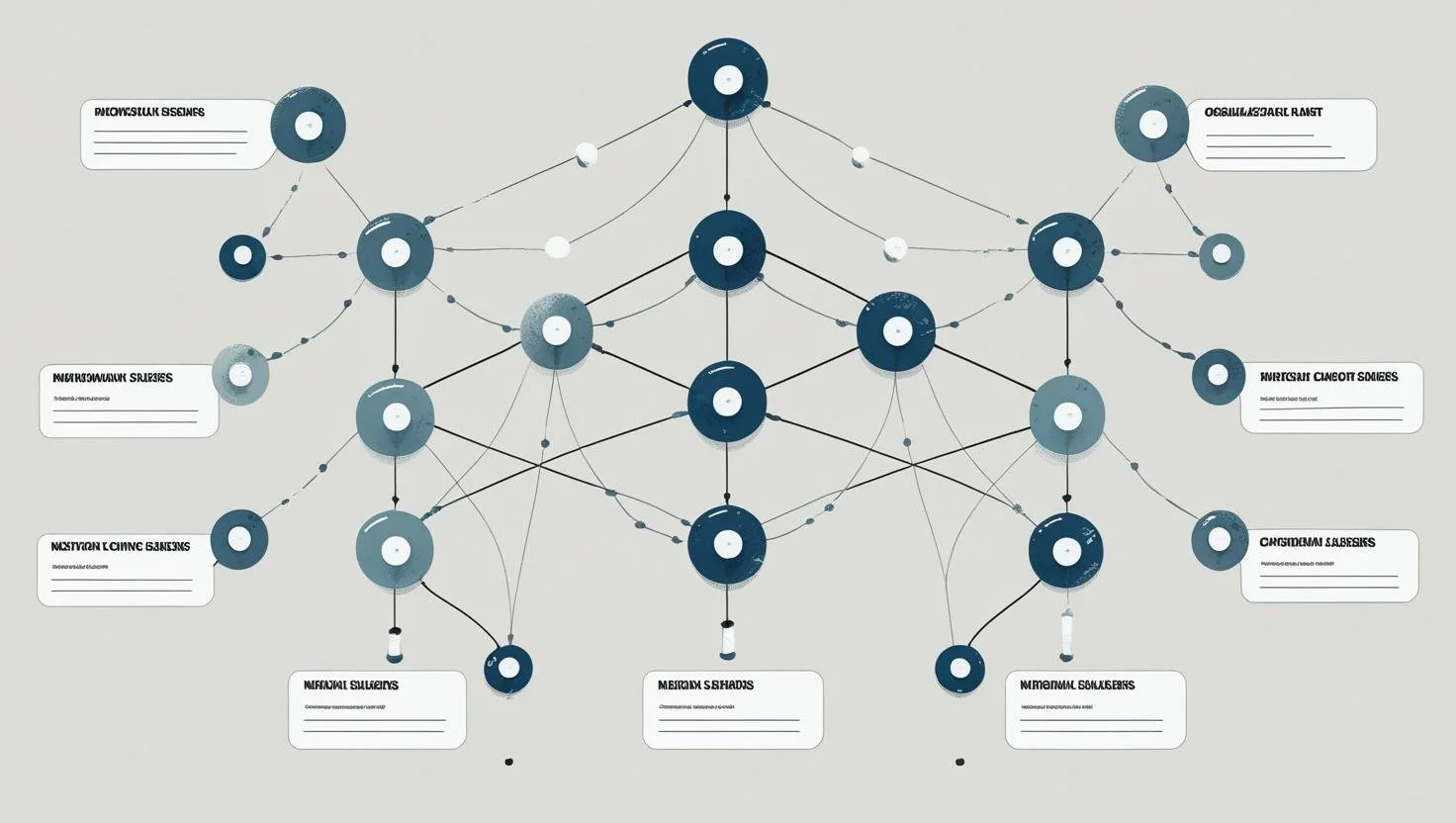「考えなくていい仕組み」と「考える力が育つ仕組み」の違いとは?
最近、こんな問いが浮かびました。
「教育の仕組み化として最初から成功のやり方を教われば、失敗せずに成長できる。
それって、本当に“いいこと”なんだろうか?」
今日は、「仕組み化」という便利な武器の“光と影”を、整理してみたいと思います。
1. 仕組み化ってなに? 〜定義と目的〜
仕組み化とは、仕事のやり方や判断基準を“型”として明文化し、誰でも再現可能な状態に整えること。
目的は大きく2つあります。
① 楽をするため
→ 毎回考えなくても迷わなくても、一定の成果が出るようにする
② 節約するため
→ 時間・人手・失敗・教育コストなど、あらゆるムダを減らす
これはつまり、“がんばらなくても成果が出る”状態をつくること。
2. 仕組み化がもたらす「楽と節約」
仕組み化されている業務は、思考や経験のコストを大幅に減らせます。
知らなくてもできる(=学ぶ時間を節約)
やらなくてもわかる(=経験コストを節約)
どう動けばいいか迷わない(=判断を節約)
成功のパターンを模倣できる(=成果への最短ルート)
結果として、失敗の確率が下がり、成功の確率が上がる。
これが仕組み化の大きな恩恵です。
3. 仕組み化の“弊害”とは?
一方で、便利すぎる仕組みは人の「成長の芽」を摘むこともあります。
自分の頭で考えない
試行錯誤しない
背景理解がないまま“こなす”だけになる
● 主体性が奪われ、受動的な風土が生まれる
「どうせ全部決まっているから、言われた通りにやろう」
「間違えるくらいなら、指示を待っていた方が安全」
こうした心理が広がると、現場には“考えない方が安全”という文化が定着します。
これでは、イレギュラー対応力や本質理解が育ちません。
成果の再現性は高まっても、
人の成長の再現性は下がる——これが仕組み化の影の側面です。
4. 「センスだから頑張れ」「やっていきながら体で身体で覚える」そんな風に言われがちな仕事こそ、仕組み化すべき理由
現場で特に厄介なのが、
「これは感覚だから」「センスでやるものだから」
とされる仕事。
でも実際には、それは言語化する方法を知らない、もしくは言語化がめんどくさいだけということも多いです。
なぜその判断に至ったのか
何を基準にそう動いているのか
どう感じて、どのように選んだのか
これらを「教える側」が分解し、言語化しようとすること。
それ自体が教育者の思考力を磨き、技術の継承性を高める行為です。
5. 次の記事→→→
「仕組み化する領域・しない領域の見極め方」
「具体的に組織で機能する仕組みの作り方」
について整理していきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。